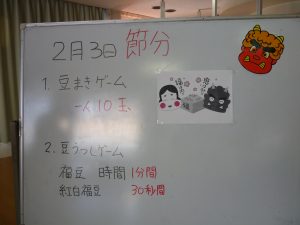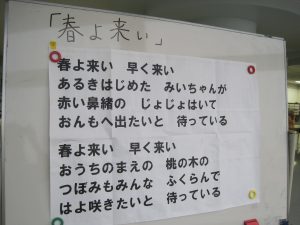第1病棟心理教育ミーティングのご紹介
第1病棟では、心理教育ミーティング(全5回1クール)を行っています。疾病理解と再発予防を目的として、精神科の病気について、薬物療法やストレス、再発のサイン、退院後の生活について考え、学び、自身の体験に照らし合わせながら理解を深めています。
今回は「再発のサイン」をテーマに挙げました。自身の病状や治療経過を振り返りながら、再発予防のため、そしてもし再発のサインが出てきたらどのように対処していくか考えていきます。再発するまえの前兆(サイン)として「思考力が硬くなった(柔軟に考えにくくなった)」「薬を飲んでも眠れないので眠前薬を飲むのをやめてしまった」「仕事に行きたくなくなった」などの意見が上がりました。その背景を伺うと、日々変わらない現状に疲弊したリ、悲観的な気持ちを自覚されていた方が多く見られました。その時点で何かしらの対処ができていればよかったのですが、大抵の方はどうすることもできず、病状・感情コントロールがうまくできなくなり、入院に至ってしまったというプロセスをそれぞれに振り返って頂けたようでした。
このような前兆(サイン)に早めに気づくことで対処の幅が広がります。何より再発しないような取り組みを考えるきっかけになるのではないでしょうか。